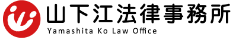目次
債権を時効にかけないためには
1 時効とは何か
まず、時効とはどういう制度なのかについて、簡単にご説明します。
時効とは、ある事実状態が一定期間継続した場合に、この事実状態に従った権利関係を認める制度です。時効には
- 権利者としての事実状態が一定期間継続した場合に権利の取得を認める取得時効
- 権利を行使しない状態が一定期間継続したときに権利の消滅を認める消滅時効
の2種類があります。今回は、消滅時効について少しご説明したいと思います。
消滅時効とは、例えば、ある人に期限を決めてお金を貸したけれども、払って貰えないまま特に請求もせず期限から5年間放置しており、その後になって貸主が借主にお金を返して欲しいと請求した際に、相手方から時効になっているので払わないと主張されると、もはや貸主のお金の返還を請求できる権利は失われてしまう、というものです(なお、時効は、単に決められた期間が経過すれば当然に効果が発生するというものではなく、時効が完成したことで利益を受ける人が時効を主張して初めて時効の効果が認められます。これを「時効の援用」といいます。)。
どうして、このような制度が認められているかについては、
- いつでも権利を行使して自分の権利を守ることが出来たのに、長期間にわたってそれを怠った以上、権利を失ってもやむを得ない
- 時間が長く経過してしまうと、事実関係に関する証拠が失われてしまう可能性が高い(例えば、お金を借りた後にもう支払いも終わると、その後長期間にわたって返済の証拠となる領収書等を保管しておくことを期待するのは酷だからです。)
などが理由として説明されることが多いです。
2 時効期間
どの程度時間が経過すると、権利が消滅してしまうのかについては、債権者が権利を行使することができることを知ってから5年間、もしくは権利を行使できるときから10年間行使しないときです。不法行為による損害賠償請求権の時効は、被害者が損害および加害者を知ったときから3年間(ただし、人の生命又は身体を害する不法行為の場合は5年間)、もしくは不法行為の時から20年間です。自分の権利を守るためには、自分の権利が何年で時効になってしまうのか、注意しておく必要があります。
3 時効の更新
次に、自分の権利が消滅時効にかからないようにするためにはどうしたら良いかについてご説明します。
時効期間は、債権者が権利を行使できる段階になったときから進行しますが(例えば、期限を決めてお金を貸したときは、その期限が過ぎるまでは借主に対して返すようには言えませんが、返済期限を過ぎれば返すように請求できるようになりますので、この時から時効期間がスタートします。)、途中で「時効の更新」が認められると、その時に時効期間がいったんリセットされて、もう一度その時点から時効期間がカウントされることになります。
この「時効の更新」が認められる場合は以下の3つです。
- 請求(ただし、裁判所が関与する正式な手続きの中で請求することが必要で、後から取り下げ等を行って権利が確定されないまま手続きが終了した場合は更新の効果が認められません。また、裁判外の手続きによる単なる催告の場合は、時効の完成をストップさせる(完成猶予)効果しかありませんので、催告から6ヶ月以内に裁判所の関与する手続きを執る必要があります。)
- 強制執行(差押えなど。)
- 承認(債務者が債務を負っている事を認めたり、明示的に認めなくても債務の存在を前提とする行為をしたりした場合を指します。)
自分の権利を時効で失ってしまわないために、時効を更新する一番簡易な方法は、③の債務者の承認をとることです。例えば、借金の一部を返済してもらえれば、通常貸金債権全体について時効の更新の効果が発生します(ただし、複数回にわたって金銭を貸し付けた場合、一部の返済では複数回の内の一つのみに時効の更新が発生する可能性がありますので注意が必要です。)。その他にも、債務がある事を認める旨を書面に一筆書いて貰うという方法も考えられます。
ただし、債務者が非協力的な場合は債務の承認を取ることは難しいので、時効期間が経過してしまう前に、①や②の裁判所が関与する手続きで請求しなければなりません。
4 時効期間が経過してしまったら
時効期間が経過してしまうと、債務者の方から時効を援用されてしまうので、基本的には権利が消滅してしまいます。
但し、債務者が時効期間が経過していることに気づかずに、債務があることを前提とした行為(これを自認行為といいます。)をした場合には、信義則上時効を援用できなくなる場合があるため、債権者としては債務の履行を請求できるようになることがあります。債権者としては、時効期間が経過してしまっていても、債務者に自認行為がなかったか十分検討する必要があります。
5 最後に
以上簡単に時効の制度をご説明しましたが、他にも問題となる事項もありますので、時効について悩まれた場合には、一度弁護士にご相談いただければと思います。