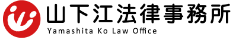目次
労働条件は簡単に変更できるの?
企業が、労働者にとって不利益な形で、賃金や賞与を変更するときなど、労働者に不利益に労働条件を変更する場合、企業はどのような手段を用いればよいのでしょうか。また、労働者は、その変更を争えるでしょうか。
企業が労働条件を不利益変更するパターンは、いくつかの場面を想定できます。多いパターンとしては、就業規則で定められている労働条件について、就業規則を変更する場合です。この場合、就業規則の変更の効力を労働者に及ぼす方法としては、2つ考えられます。
一つ目は、就業規則の変更について、労働者との間で個別の「合意」を得ることです。
二つ目は、就業規則の変更について、労働契約法が定める「合理性」と「周知性」を充たすことです。
では、一つ目の「合意」の有効性は、どのように判断されるでしょうか。
合意の有効性は、労働者の自由な意志に基づいているかという点がポイントです。これは、労働者が対等な立場で企業と交渉できないという実態を踏まえたものです。より具体的には、3つの視点で判断します。
まずは、①労働条件の変更により労働者が受ける不利益の内容や程度です。
次に、②就業規則の変更を受入れる旨の労働者の行為(例えば、同意書への署名押印など)がされるに至った経緯や態様です。例えば、労働者を恫喝して同意書に署名・押印した場合には、合意は否定されやすいでしょう。
次に、③労働者への情報提供や説明内容です。例えば、労働条件の変更について、全く説明がない場合には、合意が否定されやすい方向に働きます。
それでは、二つ目の「合理性」と「周知性」は、どのように判断されるでしょうか。
ここでいう「周知」とは、労働者が知ろうと思えば知ることができる状態に置くことです。
「合理性」は、次のとおり、5つの視点(①~⑤)で判断します。
最初に、①労働者の受ける不利益の程度と②労働条件の変更の必要性です。例えば、賃金や賞与などを大幅に減額する場合には、労働者にとってダメージが大きといえますから、より一層、変更の必要性が求められます。
次に、③変更後の就業規則の内容の相当性です。例えば、労働者が受ける不利益を緩和する措置として、代償措置や経過措置がなされている場合には、合理性を肯定する方向に働きます。
次に、④労働組合等との交渉の状況です。例えば、労働者の多くが加入している労働組合との間で合意をしている場合には、合理性を肯定する方向に働きます。
最後に、⑤その他の事情です。例えば、就業規則の変更について、労働基準法が定める届出や意見聴取を行っている場合には、合理性を肯定する方向に働きます。
当事務所では、このような複雑な労働条件の不利益変更などの労働問題について、依頼者・相談者が企業側か労働者側かにより、それぞれの立場に立って問題を解決していきます。労働に関する問題がありましたら、当事務所にご相談ください。