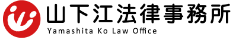仕事を休んでも賃金が減額されない「有給休暇」ですが、この有給休暇の取得には義務があるということをご存じでしょうか。今回は有給休暇の取得義務についてお話しします。
まず、前提として有給休暇について基本的なことを確認しておきましょう。
労働基準法では、雇入れの日から6か月間継続勤務し、その全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、原則として10日以上の有給休暇を与えなければならないとされています。パート・アルバイトなど所定労働日数が少ない労働者についても、労働日数に応じて比例的に有給休暇を与えることになっています。
また有給休暇を与えるタイミングについては、原則として労働者が指定した時季に与えることとされています。
しかし、職場に有給休暇を取得しにくい雰囲気があったり、労働者自身が有給休暇について正しく認識していないなど、必ずしも有給休暇が適切に取得されていない実態がありました。
そこで、2019年4月に労働基準法が改正され、有給休暇が適切に取得されることを促し、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的に、有給休暇取得義務の制度が設けられました。
この義務の対象となる労働者は、有給休暇が10日以上付与される労働者であり、正社員だけでなくパートやアルバイト等も含みます。
次に、義務の内容は、使用者は労働者ごとに有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内の5日について有給休暇を取得させなければならない、というものです。
また、有給休暇を取得させるにあたり、使用者は労働者の意見を聴取しなければならず、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるように、労働者の意見を尊重するよう努めなければなりません。
使用者がこの義務に違反した場合、30万円以下の罰金が科されるおそれもあります。
したがって、使用者側は、各労働者の有給休暇の取得状況についてきちんと管理して計画的に取得させることが求められますし、労働者側も自身の有給休暇について正しく把握しておくことが重要です。
ここ数年の一連の働き方改革では、有給休暇取得の義務化の他にも労働時間の上限規制など多くの制度改正が行われています。お困りのことがありましたら当事務所にご相談下さい。
 執筆者 弁護士 稲垣 洋之
執筆者 弁護士 稲垣 洋之
プロフィール
広島県広島市出身。修道高校卒業、一橋大学法学部卒業。2005年11月司法試験合格、2006年4月最高裁判所司法研修所入所、2007年9月司法修習終了後、広島弁護士会に登録。山下江法律事務所に入所。
主な取扱分野
交通事故、債務整理、消費者事件、離婚、相続など民事・家事事件全般、刑事事件など