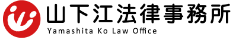目次
中小企業も注意! 割増賃金の正しい知識
労働基準法は労働者を過酷な就労環境から守るために様々な定めを置いております。
労働時間については原則として1日8時間、週40時間が上限となっておりますし、使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1回は休日を与えなければなりません。(業種や規模、また労使協定などにより例外はあります。)
使用者は労働組合(労働組合がない事業所の場合には労働者の過半数を代表する者)との書面による協定により、時間外や休日の労働を命じることが出来ます。ただし、時間外労働や休日労働に関しては労働者の負担が大きいため、使用者に割増賃金の支払いが義務づけられています。(時間外労働とは、法定労働時間をこえる労働をいい、休日労働とは法定休日における労働をいいます。)
まず、時間外労働については原則2割5分以上、月60時間を超えた時間外労働については5割以上の割増賃金の支払いが必要です。(中小企業については60時間を超えた部分の5割割り増しの規定の適用は猶予されていましたが、令和5年4月1日以降は中小企業においても適用されます。)
次に、休日労働ですが3割5分以上の割増賃金の支払いが必要です。
また、午後10時から午前5時までの間の労働については深夜労働にあたり、2割5分以上の割増賃金の支払いが必要です。
このように、割増賃金の定めを置くことにより、労働者に対してはその負担を金銭的に補填させることが出来、使用者に対しては過度の時間外労働、休日労働を抑制させる効果が期待出来ます。
なお、時間外労働が深夜に及んだ場合には時間外労働と深夜労働の二重の負担を考慮して5割以上、休日労働が深夜に及んだ場合には休日労働と深夜労働の二重の負担を考慮して6割以上の割増賃金の支払いが必要です。
以上は労働基準法に定められた最低限の割増賃金の説明です。各会社の就業規則等により労働基準法よりも広い範囲で割増を認める規定があることも多く、その場合はそれが優先します。例えば週休2日制を採用している会社の場合には、割増賃金の支払いが必要な休日は週1日の法定休日だけなのですが、法定外休日についても割増賃金の定めを置いていることも多いようです。
法定の労働時間を超えても割増賃金どころか残業代すら支払いをしていないケースも散見されます。割増賃金の支払いについて疑問があれば当事務所へご相談ください。