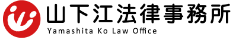目次
パワハラとは?
パワハラという言葉を聞いて、聞いたことがないという方はほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか?
しかし、具体的にパワハラとはなにかと聞かれると、漠然としたことは理解できるけれども、どのような場合に問題になるのか、という話になるとよく分からないという方もいらっしゃると思います。
今回はどのような場合に違法なパワハラになるのかについてお話ししたいと思います。
パワハラとは「パワー・ハラスメント」の略語です。実は外国語ではなく、日本のコンサルティング会社の方々が考えた造語であり、2002年頃から急速に広がった和製英語です。
パワハラの定義ですが、職権などのパワーを背景にして、本来の業務を超えて、継続的に人権と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く環境を悪化させ、あるいは雇用不安を与えることをいいます。
それでは、会社で上司が部下を注意・指導することはパワハラになるでしょうか?
この点、組織である以上、部下の業務に問題があれば、これを是正するために注意をするのは当たり前のことです。原則として、上司が部下を注意・指導することは当然許されるというべきです。
しかし、注意・指導も度を超すと人格権侵害として違法となり、パワハラとして損害賠償の請求を受けることになると考えられます。
では、どのような場合に「度を超した」として違法と評価されるのでしょうか?
この点について、明確な基準を設けるのは難しいところですが、過去の裁判例などを検討すると、
- 動機・目的が正当であるか否か
- 内容が通常の注意・指導の範囲といえるか否か
という観点から考えていくことが適当だと思います。
すなわち、1についてみると、当該従業員に特に落ち度がないにもかかわらず、厳しく注意をすれば、目的が正当とはいえず、違法性が認められやすいといえるでしょう。また、2については、感情的に激しく叱責したり、人格を否定するような言動をすれば、通常の注意・指導の範囲を超えるとして違法性が認められやすいといえます。逆に、暴力を振るわず、人格を非難せず、人前でなく別室で注意する、叱責した場合も後で優しい言葉をかけるなどフォローをする配慮をしていれば、正当な注意・指導と評価されることになると思われます。
現在パワハラの被害に遭っている、また、従業員の中にパワハラをしていると思われる者がいるが会社としてどのように対処すべきかわからない、などの問題でお悩みであれば、当事務所までお気軽にご相談下さい。
 執筆者 弁護士 柴橋 修
執筆者 弁護士 柴橋 修
プロフィール
広島県安芸郡熊野町出身。広島大学附属高校卒業、早稲田大学法学部卒業。2002年11月司法試験合格、2003年4月最高裁判所司法研修所入所、2004年10月司法修習終了後、広島弁護士会に登録。山下江法律事務所に入所。
主な取扱分野
交通事故、債務整理、消費者事件、離婚、相続など民事・家事事件全般、刑事事件など